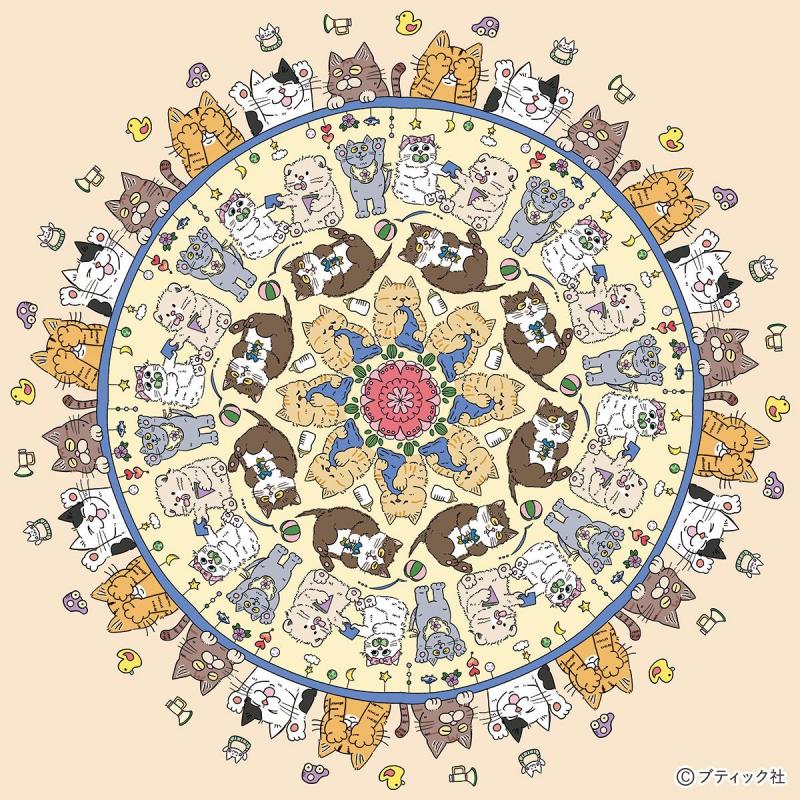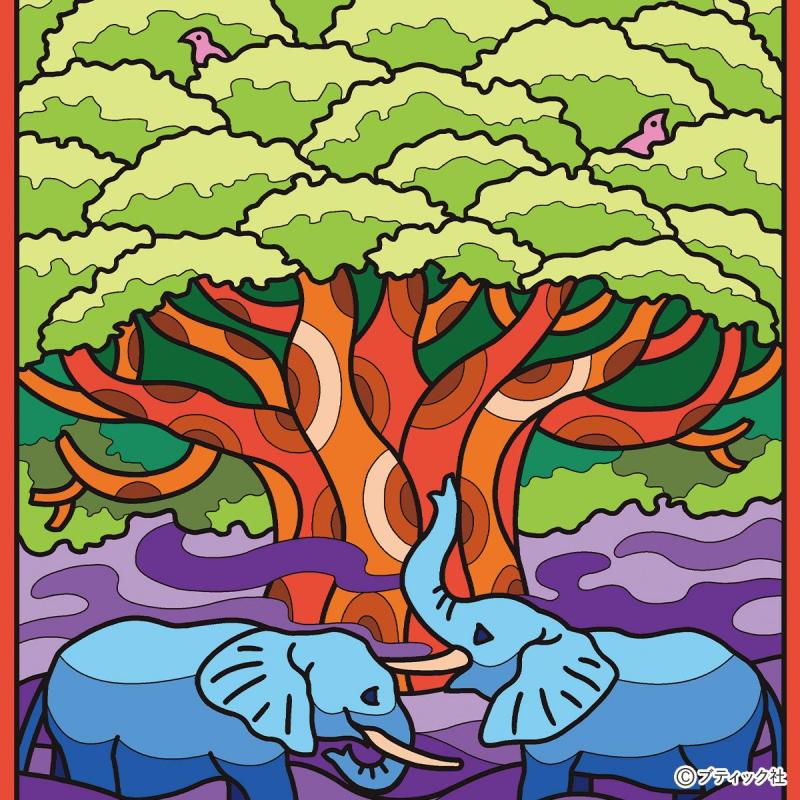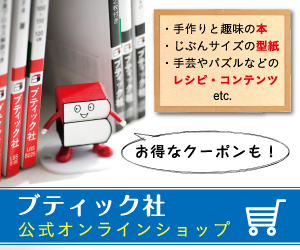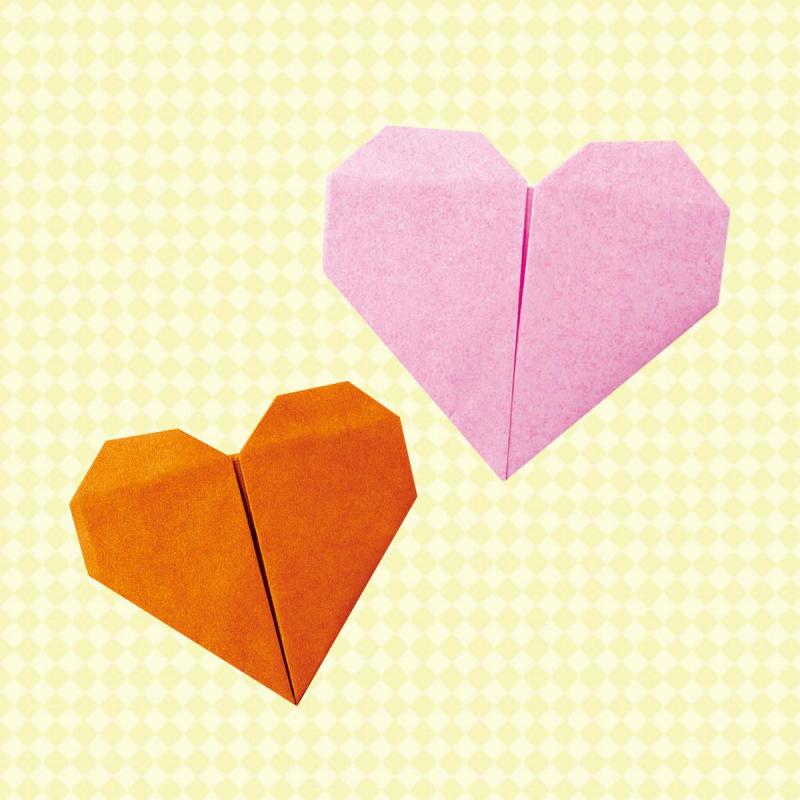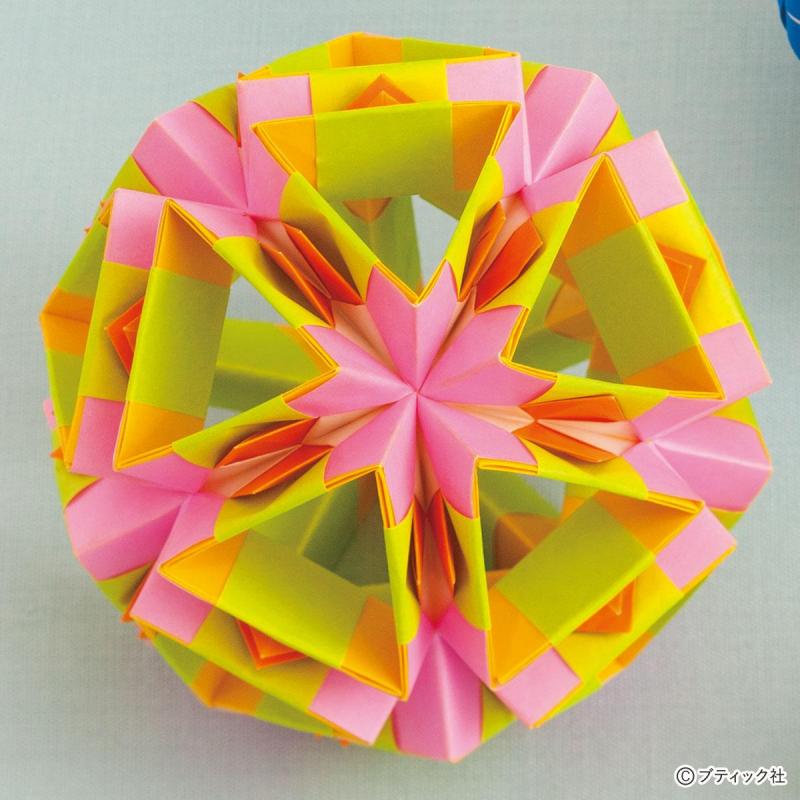トマトとは?(特徴)
さまざまな料理で幅広く親しまれているトマト。栄養も満点で、完熟してすぐに食べられるトマトのおいしさは格別です。
・ナス科
・栄養/ビタミンA、C、ミネラルなど
・性質/日なたを好み乾燥に強い
・病害虫/アブラムシに注意
・連作/2~3年は不可
種まきと収穫に適した時期
■種まき:4~5月頃 ■収穫:7~8月頃
※野菜作りにはそれぞれに適した時期があります。
※関東地方を基準としたものです。関東より暑い地方や寒い地方で栽培する場合は時期の調整が必要です。
上手に作るためのポイント
★日当たりと水はけのよい場所で作る!
トマトは、水はけが悪く地表に水がたまるような環境だと、根が腐って枯れてしまいます(これを根腐れといいます)。
水はけ・風通しがよくなるよう、堆肥を与えてうねを高くして植えつけます。
★病気に強い品種を選ぶ!
一代交配やF1などの品種は、病気にかかりにくいように改良されているので、これらの品種を選びましょう。

育て方
1. 土を改良する
トマトは酸性に強いのですが、好石灰植物と言って、石灰や苦土が必要です。そこで、苗を植え付ける2週間前に、畑に1平方メートル当たり苦土石灰200g、ようりん150gを施し、よく耕します。
2. 元肥を入れる
苗を植えつける1週間前に、うね幅(80~90cm)に合わせて溝を掘って、堆肥を入れます。溝の深さはなるべく深く20cm以上にします。これに過リンサン石灰を1平方メートル当たり100g加えます。
最初に入れる堆肥や化成肥料などの肥料を元肥といいます。堆肥は半熟でもよいので、なるべく多く入れましょう。
堆肥がなければ草木を刈って入れても効果があります。堆肥がなくて草やワラを入れた時は、硫安を40g追加します。
トマト作りではチッソ肥料を元肥に多く施しすぎると、葉や茎の大きさのわりに実のつきが悪くなることが多いので、実ができるまではチッソ肥料を控え、実の肥大しはじめるころにチッソ肥料を施すと、実がたくさんとれます。
そこで、元肥を入れるときは、チッソ肥料(硫安)を離して施し、リンサン(ようりん・過リンサン石灰)・カリ・化成肥料がはじめに効くようにします。
3. うねを作る
掘り上げた土をもどして、化成肥料を1平方メートルあたり60g全面にまいて土によく混ぜます。元肥が土によく混ざったら、うねを高く作ります。

4. 苗を用意する
4月下旬~5月上旬に園芸店で苗を購入します。トマトは果実を収穫する野菜ですから、つぼみが充実していることが大切です。
苗は小さくても、芽先につぼみがあるものを選びます。大きくても芽先につぼみがないものは避けましょう。
5. 苗を植えつける
苗を植える穴を掘ります。トマトは水はけがよいとよく育つので、穴の深さは浅くします。苗についている土の部分がすっぽり入るのが適当です。
植え穴の底にたっぷり水をかけておきます。植え穴に苗を植えつけ、また、水をかけます。茎がグラグラする場合は、支柱を立てて、ひもで茎と支柱を8の字型に軽く結んでおきます。これが苗が生長する間の仮支柱です。